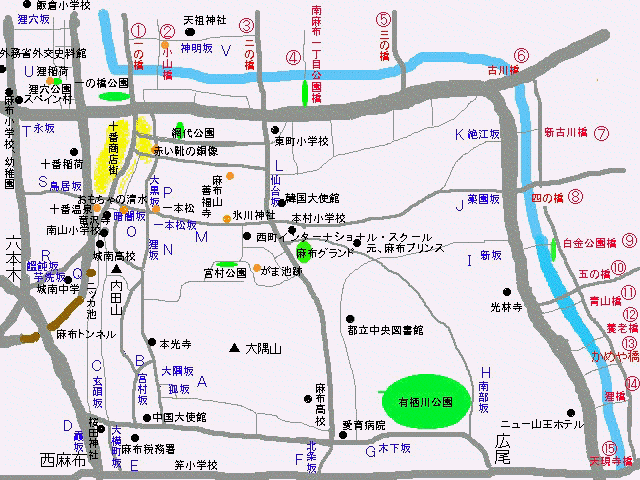麻布地図
麻布な地図、麻布な橋、麻布な坂(地図をクリックして下さい。)
麻布北東部地図はこちらから。 Google Map DEEP AZABU
●麻布の橋
赤羽橋
中の橋
新堀橋
① 一の橋..........芝南新門前2丁目台地から西にかけた橋。(文政町方書上)
②小山橋.........私道の橋が昭和30年5月20日区の管理に。
③二の橋..........毛利日向守の屋敷があり日向橋とも。(御府内備考)
④南麻布一丁目公園橋...不明。
⑤三の橋..........松平肥後守の屋敷わきなので肥後橋とも。(文政町方書上)
⑥古川橋...........明治37年5月私設の橋を市に編入。(東京案内)
⑦新古川橋..........昭和8年地図上に現れた橋。詳細不明。
⑧四の橋..........土屋相模守屋敷があるので相模橋、麻布薬園があったので薬園橋とも。(文政町方書上)
⑨白金公園橋........不明。
⑩五の橋..........昭和10年9月6日架橋。
⑪青山橋.........持ち主個人の名の橋で私設橋。現在は通行止め。
⑫養老橋.........明治の頃でき元は、個人がかけた橋。
⑬かめや橋........明治の後半に出来た橋。これも個人がかけた橋。
⑭たぬき橋.......三光町に”たぬきそば”があるのでついた名。元禄の地図にも載る古い橋。
⑮天現寺橋........元禄の地図にはある古くからある橋。詳細不明。
広尾橋
笄橋
網代橋
●麻布の坂
●麻布周辺
- ○大隅坂、(別名:きつね坂)
- PHOTO GALLERYでこの坂をきつね坂と書いたが、先日、宮村のたばこ屋に遊びに行ったとき、ご主人に大隅坂だと教えて頂いた。 本光寺の裏山が大隅山と言う。これは、江戸時代に渡辺大隅守の上屋敷があったからとの事。では、きつね坂はと言うと、 大隅坂を登り左に曲がった路地との事。昔は麻布高校も無かったので緩やかな坂が続いていた と思われる。
- ○宮村坂
- この坂は昭和になってから出来たらしい。それ以前は行き止まりだった。宮村町へ下るから付いた名だろうが、江戸時代には、暗闇坂を宮村坂とも呼んだらしい。
- ○玄碩坂
- 玄碩(げんせき)と言う名の僧が住んでいたので付いたらしい。別名を薮下坂とも言う。 こちらは、薮下町へ下るため。
- ○霞坂
- 昔、このあたりは霞町と言う町名で、西麻布交差点は、霞町交差点だった。 坂の歴史は比較的新しく、明治の初め霞山稲荷(現桜田神社)のあるこのあたりを霞町とし、 新しく作られた坂を、霞坂と名付けた。 昔の深夜放送で”霞町交差点のおばけ都電”と言う話を聞いた覚えがある。 反対の高木町へ登る坂は、笄(こうがい)坂。
- ○大横町坂(別名:富士見坂)
- ○北条坂
- 江戸時代、坂の中ほどに狭山藩北条(小田原の後北条)家の下屋敷があったため。
- ○木下坂
- 坂の西側が木下備中守の上屋敷だった為。
- ○南部坂
- 盛岡藩南部家の下屋敷があったため。現在有栖川公園、中央図書館、麻布グランド、 があるあたりはすべて南部藩邸であったらしい。 私の小さい頃、このあたりは盛岡町であり、麻布グランドは盛岡グランドであった。
- ○薬園坂
- 江戸の初期(寛永年間)にこのあたりに幕府の薬草園があり、輸入した薬草などを栽培していた。 後に薬草園は小石川に移転したが、坂名だけは残った。
- ○新坂
- 明治の頃に新しく作られた坂らしい。坂下の光琳寺には二の橋で暗殺された アメリカ公使館通訳ヒュ-スケン、イギリス公使館通訳伝吉が眠っている。
- ○絶江坂
- 落語”黄金餅”にも登場する坂。江戸初期(承応年間)、坂の東面の曹渓寺に絶江と言う高名な住職がいたため、そのままこのあたりの 地名になった。ここには、赤穂浪士のひとり寺坂吉衛門が眠る。ちなみに黄金餅の”麻布絶江もくれん寺” は架空の寺で、実在しない。
- ○仙台坂
- 現韓国大使館のあたりに、仙台藩伊達家の下屋敷があったため。品川区大井町にも同名の坂があり 理由は同じ。ちなみに大井町の方は、坂上に今も仙台味噌屋がある。
- ○一本松坂
- 狸坂、暗闇坂、大黒坂の合流点から氷川神社方面へ上がる坂。 名前の由来は、麻布七不思議の一つ”一本松”があるため。
- ○狸坂(別名:朝日坂)
- 一本松から宮村町へと下る坂。坂の下まで昔は一本松町と言った。名の由来は、昔から大正時代くらいまで本当のたぬきが住み着いていたらしい。 別名は旭坂。
- ○暗闇坂
- つい最近まで、大使館と屋敷に挟まれ両側から木が鬱蒼と茂り、昼でも薄暗かったような気がする。 江戸の初期まで、この坂の西面から狸坂の東面までの広大な敷地に氷川神社はあったらしい。
- ○大黒坂
- 坂の途中に港区七福神の一つ、大黒天の大法寺があるため。小さい頃、節分の豆撒きに行くのが 楽しみだった。ちなみにこちらのご息女は、私の幼稚園の先生だった。
- ○芋洗坂
- 途中に芋屋があった、芋を洗う池があった、などと言われる。また芋とは疱瘡のことで、芋を洗うとは、疱瘡を治すことと言う説もあり そのような病に効く神様を祭った祠があったとも......
- ○饂飩坂
- 鈴木伊兵衛と言う”うどん屋”があった為。
- ○鳥居坂
- 江戸時代、鳥居家の屋敷があったためとも、坂の上に氷川神社の二の鳥居があったためともいわれる。
「十番わがふるさと」によると、「幼い頃、鳥居の礎石で遊んだ」と言う宮村町の古老がいたという。
- ○永坂
- 長坂とも言う。やはり坂が長いためついた名。永坂と言えば更科そば。”更科”とは、信州更級の字を領主の保科にあわせ更科としたそうだ。 ちなみに保科家は二代将軍秀忠の子から始まり、幕末の京都守護職、松平容保の先祖である。 ここの名物は御前そば。増上寺に献上したのが始まりでやがて評判になり、江戸の頃より著名人が食した。しかし値段もほかと比べて高く、 太田蜀山人に「更科のそばはよけれど高稲荷(たかいなり)森(盛り)を眺めて二度とコンコン(来ん、来ん)」と読まれた。
- ○狸穴坂
- ソ連大使館横の坂。ここもやはり狸が生息していた。昔この坂のあたりに、古洞があり鉱山だったとも 狸の巣とも言われる。坂の下にアメリカンクラブが在り、その奥が古洞だとすると....007だ!
○神明坂(三田小山町)
天祖神社のあるために付いた。別名、芝元明神。(むかし、むかし参照)
○三光坂(白金)
○南部坂(赤坂)
○乃木坂(赤坂)